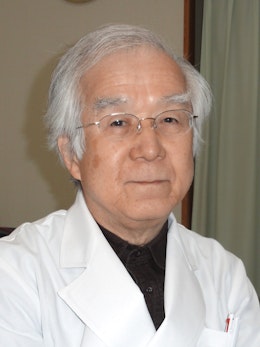大動脈瘤の原因・症状・治療法と予防のポイントを解説
医師紹介
大動脈瘤とは
大動脈は心臓から血液を送り出すもっとも太い血管です。大動脈瘤は、この大動脈が部分的にふくらんで、こぶ状(瘤)になる疾患です。
大動脈瘤の発生した場所が、胸とおなかの境目にある横隔膜より上であれば「胸部大動脈瘤」、横隔膜から下であれば「腹部大動脈瘤」と呼ばれます。治療せず放置をすると、徐々に大きくなって前触れなく破裂し、突然死につながることもあります。
原因
ほとんどの場合、血管が硬くなる「動脈硬化」が原因となって起こります。動脈硬化によって硬くなった血管の壁がもろくなることで、その部分に大動脈瘤ができやすくなります。
そのほかにも、事故などの外傷や感染症、炎症などが原因となる場合があります。
症状
破裂するまでは無症状なことがほとんどです。
大動脈瘤の大きさなどによっては、発生した場所に応じて、以下のような症状があらわれることがあります。ただし、このような症状があらわれる状態は、大動脈瘤が破裂する危険性も高まっている可能性があります。
〇 胸部大動脈瘤の主な症状
- 飲み込みづらさ(嚥下困難)
- 声のかすれ(嗄声)
- 血痰
など
〇 腹部大動脈瘤の主な症状
- 腹部の拍動感
- 腹痛
- 腹部の不快感
- 腹部の張り(膨満感)
- 食欲低下
など
大動脈瘤が破裂 もしくは 破裂する寸前(切迫破裂)の状態になると、多くの場合、胸部や腹部、背中、腰のあたりに急激な激しい痛みが起こります。また、破裂して大量出血を起こすと、失神などの意識障害を起こすショック状態や突然死に至る可能性があります。
検査・診断
主に、レントゲン検査や超音波(エコー)検査、CT検査、MRI検査などの画像検査で、大動脈の状態を確認します。さらに、大動脈瘤の大きさや位置などの詳細な状態の確認や、手術の必要性や方法の検討のためには、造影剤を血管に注入して行う造影CT検査や造影MRI検査などが行われます。
治療・治療後の注意
主に、「内科的治療」「血管内治療」「外科的治療」があります。どの治療を選択するかは、大動脈瘤の大きさや位置、形、全身の状態などをもとに検討されます。
内科的治療
大動脈瘤の大きさや状態によっては、経過観察が選択される場合もあります。その場合は、定期的にCT検査などを行い、大動脈瘤の大きさや状態を確認します。また、悪化や破裂のリスク要因となる高血圧や脂質異常症、糖尿病などがあれば、その管理や治療も行われます。喫煙習慣も、同じく悪化や破裂の大きなリスク要因となるため、禁煙が推奨されます。
血管内治療(ステントグラフト内挿術)
足の付け根の血管から、大動脈瘤のある部分までカテーテルを挿入し、大動脈瘤の内側に人工血管(ステントグラフト)を留め置く治療です。そうすることで、大動脈瘤には直接 血液が流れなくなるため、破裂を防ぐことができます。身体への負担が少ないため、合併症や高齢などが理由で、外科的な治療のリスクが高い場合は、特に優先して検討される治療です。
外科的治療(人工血管置換術)
胸部や腹部を切開して行う手術です。大動脈瘤のある血管を取り除き、人工血管に置き換えます。
予防
大動脈瘤の要因となる動脈硬化を防ぐことが予防につながります。動脈硬化が起こるリスク要因は、喫煙や肥満、脂質異常症、高血圧、糖尿病など、生活習慣と密接に関係していることが多いため、健康的な食生活、適度な運動など、生活習慣を整えることが予防につながります。特に喫煙は大きなリスク要因なので、積極的に禁煙をしましょう。すでに生活習慣病(脂質異常症、高血圧、糖尿病など)にかかっている場合も、適切な治療を受け、よりよい状態にコントロールすることが予防につながります。
医師紹介
1978年 佐久総合病院 (1987年より内科 および 集中治療室医長)2007年 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院副院長2019年 佐久総合病院総合内科専門医(日本内科学会) 、循環器専門医(日本循環器学会)、救急科専門医(日本救急医学会)、集中治療専門医(日本集中治療医学会)、超音波専門医(日本超音波医学会)。専門分野は一般内科、循環器内科。