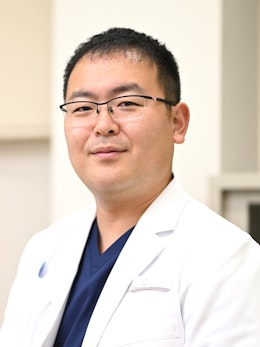膀胱結石の原因・症状・治療法と予防のポイントを解説
医師紹介
膀胱結石とは
尿の通り道である、腎臓→尿管→膀胱→尿道のいずれかに結石(石状の異物)が留まり、排出できなくなる疾患を総称して尿路結石と呼びます。そのうち、尿を一時的に溜めておく臓器である膀胱に、結石(石状の異物)が留まり排出できなくなる疾患です。
原因
主に以下のようなことがきっかけとなり、腎臓や尿管で発生した結石が膀胱で留まる場合と、膀胱内で発生した結石がそのまま留まる場合があります。
排尿機能障害
排尿がうまくいかず、残尿が多くなる状態です。この状態だと、通常であれば排尿の際に一緒に身体の外に排出される結石が、膀胱内に留まり続ける原因になります。また、留まり続けることで、結石が大きくなり、さらに排出されづらい状態になります。
特に、以下のような疾患は排尿機能障害を起こしやすく、膀胱結石の原因になることがあります。
前立腺肥大症 / 神経因性膀胱 / 尿道狭窄 / 膀胱憩室 など
膀胱カテーテルの留置
何らかの目的で膀胱にカテーテルが挿入されていると、その周囲に結石が生じ、膀胱で結石がつくられる原因になることがあります。
これ以外にも、結石が発生、留まる要因はさまざまです。生活習慣に関連することも多く、不健康な食事習慣や肥満、水分の摂取不足などが要因としてあげられます。そのほかにも、代謝異常や内分泌疾患など、特定の疾患に関連する場合や、遺伝性の要因で発生する場合もあります。一方で、原因がわからないこともめずらしくありません。
症状
主な症状には以下のようなものがあります。
〇 主な症状
- 排尿時の痛み
- 血尿
- 頻尿
- 残尿感
- 排尿困難(うまく尿が出ない)
- 下腹部の異物感
- 下腹部の痛み
など
検査・診断
一般的な問診や診察で、膀胱結石をはじめとする尿路結石が疑われた場合は、超音波(エコー)検査やレントゲン検査、内視鏡検査などで結石の有無を確認します。このような検査では見つけられないなどの場合は、CT検査を行うこともあります。そのほか、尿検査や血液検査などが行われます。
治療・治療後の注意
尿路結石の中でも膀胱結石は、結石が比較的太い管である尿道を通ることができない状態になっていることで起こります。そのため、基本的に自然に排出するのは難しいことから、以下のような外科的治療が中心に行われます。
年齢や、全身や結石の状態,年齢、持病などの理由で、外科的治療が難しい場合は、薬物治療など、ほかの治療方法が検討されることがあります。
経尿道的尿管結石破砕術・けいにょうどうてきにょうかん けっせきはさいじゅつ(TUL)
尿道から結石のある場所まで内視鏡を挿入し、レーザーなどを用いて結石を砕いて、取り除きます。麻酔をして行うため、数日間の入院が必要です。膀胱結石における外科的治療の中で、最も一般的な治療方法です。
開腹手術
下腹部と膀胱を切開して、結石を取り除く方法です。現在ではほとんど行われません。どの方法でも結石が排出されない または 取り除けなかった場合などにまれに行われます。
予防
尿が濃くなると結石ができやすくなるので、日常的に十分な水分摂取をしましょう。そのほか、生活習慣と密接に関係している要因も多くあるため、健康的な食生活や適度な運動など、生活習慣を整えるのもよいでしょう。
また、膀胱結石をはじめとする尿路結石は、再発率の高い疾患です。確実に再発を予防することは困難ですが、再発予防としては以下のようなことが推奨されます。
〇 再発予防
食事以外で1日2,000mL以上の水分を摂取する / カルシウムを積極的に摂取する(1日600mg~800mg) / 動物性たんぱく質を過剰に摂取しない / プリン体を過剰に摂取しない(1日400mg以内) /塩分を控える / クエン酸を摂取する / 就寝前4時間は食事を控える など
医師紹介
国立病院機構災害医療センターでの初期研修を経て、日本医科大学付属病院と、山形県や神奈川県の関連病院に勤務。膀胱炎や過活動膀胱など、代表的な泌尿器疾患をはじめ、前立腺がんや腎臓がんなどの泌尿器がんに対する腹腔鏡手術や開腹手術などの外科手術、術後の管理まで、幅広い症例に携わる。そのほか、救急外来や皮膚科、内科での診療経験なども経て、2023年にこくぶんじ泌尿器科クリニックを開業。専門分野は泌尿器科一般、悪性腫瘍、性感染症。