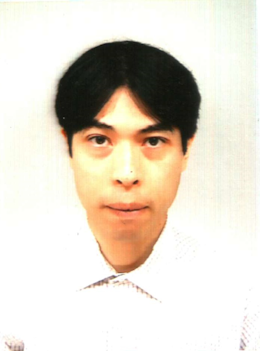糖尿病網膜症の原因・症状・治療法と予防のポイントを解説
医師紹介
糖尿病網膜症とは
糖尿病がもととなり、眼の奥に位置する網膜の血管が詰まったり、出血を起こしたりする疾患です。視力低下などのさまざまな症状が起こり、最終的には失明に至ることもあります。
原因
糖尿病が原因となって起こります。糖尿病で高血糖の状態が続くと、血管に負担がかかりダメージを受けます。その状態が続くと、やがて網膜の血管に詰まりや出血などが起こり、視力低下や失明の症状につながります。特に、糖尿病になってから5年以上経過するとリスクが高くなります。
症状
初期の段階では自覚症状はあまりみられません。状態が進行すると、血管が詰まるなどの血管障害が起こり、視界がかすむなどの症状があらわれてきます。さらに進行して末期の状態になると、視力低下や飛蚊症(視界に蚊が飛んでいるように見える症状)、網膜剥離、血管新生緑内障などが起こり、やがては失明に至ることもあります。
検査・診断
糖尿病網膜症は、糖尿病の状態の影響を大きく受けるため、まずは糖尿病にかかっているか、かかっている期間、過去および現在の血糖値コントロールの確認などの問診をします。そして、糖尿病網膜症の診断や重症度を判断するための検査として、視力検査や眼に空気などをあてて眼の硬さを測る眼圧検査、拡大鏡を使って眼の前側部分を診る検査(細隙灯顕微鏡検査)、眼底鏡などを使って眼球内部を診る眼底検査などが行われます。これらの検査で糖尿病網膜症が疑われた場合には、より正確な状態を把握するため、造影剤を注射して眼の血管や網膜を撮影する画像検査(蛍光眼底造影検査)が行われることもあります。
治療・治療後の注意
重症度によって治療方法は異なりますが、レーザー治療を基本に、重症の場合は外科的な手術が行われます。
レーザー治療(網膜光凝固術)
網膜にレーザーを当てて、問題のある部分を固めたりすることで、それ以上状態が進行しないようにします。
外科的治療(硝子体手術)
眼内の出血に阻まれてレーザーを当てられない場合や、レーザー治療のみでは抑えられない程度まで重症化している場合に行われます。眼の内側から、出血を止めたり、剥がれている網膜(網膜剥離)を元に戻したりします。
このような治療とあわせて、食事療法や運動療法、薬物治療によって血糖値のコントロールをします。
予防
糖尿病にならないことが最も有効な予防法です。そのため、健康的な食生活や適度な運動など、生活習慣を整えることが予防につながります。すでに糖尿病になっている場合は、常に血糖値をコントロールして、糖尿病を安定した状態に維持することが予防につながります。また、糖尿病網膜症は、自覚症状がほとんどないまま進行していくため、定期的に眼科を受診するなどして、眼の検査を受けるようにしましょう。
医師紹介
1998年 東京医科歯科大学病院、1999年 湘南鎌倉総合病院、2001年 川口工業総合病院、2004年 JCHO三島総合病院(2007年より眼科医長、2011年4月より眼科部長)。日本眼科学会眼科専門医。専門分野は神経眼科。