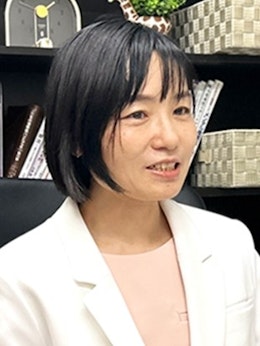自律神経失調症の原因・症状・治療法と予防のポイントを解説
医師紹介
自律神経失調症とは
自律神経には交感神経と副交感神経があり、この2種類の神経がバランスよく働くことで、体温や心拍をはじめとした、身体の内部のあらゆる状態を適度に保っています。
自律神経失調症とは、この自律神経のバランスが疲労やストレスなど、何らかの原因によって正常に働かなくなることで、心や身体にあらわれるさまざまな不調の総称です。
原因
さまざまなことが原因となり得ますが、ストレスや疲労、睡眠不足などの生活習慣の乱れが影響していることが多くあります。そのほかに、急激な気温の変化などが影響することもあります。
症状
特定の決まった症状はなく、精神的な症状から身体的な症状まで多岐にわたります。主な症状には以下のようなものがあります。
〇 精神的な症状
気分が落ち込む / イライラする / 眠れない / 食欲不振 など
〇 身体的な症状
動悸(胸がドキドキする)/ 息切れ / 疲れやすい / 倦怠感 / 頭痛 / めまい / 手足のしびれ / 胃の不調 / 下痢や便秘 / 冷えやほてり など
検査・診断
まずは内科的、運動機能的な異常や問題などからくる不調ではないかを見分ける必要があります。そのような身体的な異常や問題がないと判断されると、症状や生活状況を聴きとる問診を中心とした診察によって診断されます。
治療・治療後の注意
治療には大きく分けて「精神療法」と「薬物治療」があります。
精神療法
ストレスや疲労の原因になることがあれば、それらをコントロールする または できるだけ取り除きます。また、睡眠や食事習慣などの生活習慣に乱れがあれば整えます。悩みや不安など精神的な問題が強い場合は、医師や臨床心理士によるカウンセリングを受けるのもよいでしょう。
薬物治療
特別な治療薬はありませんが、対症療法として薬が使われます。具体的には、不安をやわらげるための抗不安薬や不眠改善のための睡眠薬、下痢や便秘の症状がある場合には整腸薬や便秘薬など、症状に応じて処方されます。
予防
ストレスや疲れが溜まったままの状態は自律神経の乱れにつながるため、十分な休息をとるなどして、ストレスや疲れを溜めないことが予防につながります。そのほかにも睡眠や食事習慣などの生活習慣に乱れがあれば改善しましょう。
また、運動をして汗をかくことは、体温調節の機能を正常に保ち、自律神経のバランスも整いやすくなります。ウォーキングや室内でできるストレッチ・軽い体操、日常でなるべく歩く・階段を使うなど、無理なくできる適度な運動をするのもよいでしょう。
医師紹介
2011年 都立松沢病院精神科医長、2020年 やまでらクリニック院長。精神科指導医(日本精神神経学会)、認定産業医(日本医師会)、精神保健判定医(厚生労働省)。専門分野は児童精神科、漢方精神科。