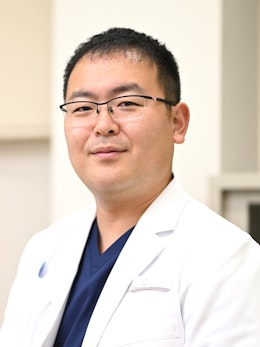尿道炎の原因・症状・治療法と予防のポイントを解説
医師紹介
尿道炎とは
尿の通る道には、腎臓→尿管→膀胱→尿道があり、このいずれかに細菌やウイルスなどが感染し、炎症などを起こす感染症を総称して「尿路感染症」と呼びます。その中でも、尿道で感染、炎症など起こすものが「尿道炎」です。特に、男性は尿道が長いため尿道での感染を起こしやすく、一方で尿道の短い女性が尿道での感染を起こすことはまれです。
原因
膀胱から尿の出口までをつなぐ「尿道」に、細菌やウイルスなどが感染することで起こります。主な原因となるのは、細菌の一種である淋菌です。そのほかにも、クラミジアやマイコプラズマ、ウレアプラズマなどの細菌や、単純ヘルペスウイルス、真菌(カビ)、トリコモナス(寄生虫)などに感染することでも起こります。
感染経路は、ほとんどが性的な接触によるもので、細菌やウイルスなどが付着した部分と性器周辺の粘膜や皮膚が接触することが感染のきっかけになります。具体的には、通常の性行為(性器と性器)やアナルセックス(性器と肛門)、オーラルセックス(性器と口)などです。そのほかにも、さまざまな粘液や体液への接触で感染する可能性もあるため、原因の特定が困難なことがあります。
症状
主な症状には以下のようなものがありますが、症状がまったくあらわれないことも多いです。
〇 主な症状
- 排尿時の痛み
- 尿道や下腹部違和感
- 尿道から膿などの分泌物が出る
など
痛みの強さや膿、分泌物などの状態は、感染している細菌やウイルスなどによって異なります。
検査・診断
症状などを聴き取る問診で尿道炎が疑われた場合は、尿検査で炎症の状態や感染有無の確認、原因となっている細菌やウイルスなどの特定をします。また、尿道から膿などの分泌物がある場合は、それを採取して検査することもあります。
感染がわかった場合は、性的な接触をしたパートナーも同じ細菌やウイルスなどに感染している可能性があるため、同様の検査を受けることが推奨されます。
治療・治療後の注意
基本的には薬物治療です。使われる薬は原因によって異なります。細菌には抗生物質、ウイルスには抗ウイルス薬、真菌(カビ)には抗真菌薬、トリコモナス(寄生虫)には抗原虫薬の中で、それぞれに適した薬が使われます。
淋菌の場合は1回の点滴 もしくは 注射で治療が完了しますが、それ以外は飲み薬による治療となります。薬を飲む期間は、1回で済むものもあれば数週間飲み続ける必要があるものなど、原因や薬の種類などによって異なります。
治療中は感染を広げてしまう可能性があるため、性的な接触全般を控えましょう。また、何らかの理由で薬の効果が十分ではなく、細菌やウイルスなどが残っていると、再発につながりやすいため、治療後2週間~3週間後を目安に、原因となった細菌やウイルスなどがいなくなり、完全に治っているかの検査を受けることが推奨されています。
予防
尿道炎にかかるのは男性が多く、ほとんどが性的な接触をきっかけに感染します。そのため、性交時だけではなく、それに関連する性的な接触の際には、コンドームを正しく使用することが予防につながります。感染を完全に予防するものではありませんが、そのほかの性感染症や、望まない妊娠などを防ぐことにもつながるので、積極的に使用しましょう。
また、感染者や感染の疑いのある相手、不特定多数との性的な接触は、感染のリスクが高くなるため避けましょう。複数のパートナーとの性的な接触がある場合には、重症化や感染拡大を防ぐためにも、定期的に検査を受けることが推奨されます。
医師紹介
国立病院機構災害医療センターでの初期研修を経て、日本医科大学付属病院と、山形県や神奈川県の関連病院に勤務。膀胱炎や過活動膀胱など、代表的な泌尿器疾患をはじめ、前立腺がんや腎臓がんなどの泌尿器がんに対する腹腔鏡手術や開腹手術などの外科手術、術後の管理まで、幅広い症例に携わる。そのほか、救急外来や皮膚科、内科での診療経験なども経て、2023年にこくぶんじ泌尿器科クリニックを開業。専門分野は泌尿器科一般、悪性腫瘍、性感染症。