頻尿の原因と対策 【医師監修】 頻尿の回数は?糖尿病やがん…病気が隠れていることも!

頻尿の原因は心因性のものや、細菌などに感染して起こるもの、内臓の病気が潜んでいるものなど、実にさまざまです。
医師紹介
目次
1日8回以上が頻尿の目安
頻尿の具体的な回数は、医療機関などによって異なる場合がありますが、日本泌尿器学会では以下のように定義されています。
〇 朝起きてから就寝までの排尿回数が8回以上の場合を頻尿といいます。しかし、1日の排尿回数は人によって様々ですので、一概に1日に何回以上の排尿回数が異常とはいえず、8回以下の排尿回数でも、自身で排尿回数が多いと感じる場合には頻尿といえます。
引用)日本泌尿器学会
頻尿の種類と原因

頻尿にはいくつかの種類やさまざまな原因があります。
ここでは、頻尿の主な種類や原因である、過活動膀胱、尿路系の異常(膀胱がん / 残尿 / 尿路系の感染や炎症)、多尿、心因性について解説します。
過活動膀胱
過活動膀胱とは、本来なら尿意を感じない程度しか尿が溜まっていないのに、勝手に膀胱が収縮してしまい、尿意を感じてしまう状態です。
〇 主な症状
・トイレにいく回数が多い
頻尿 ・ 夜間頻尿
・尿意切迫感
急にトイレに行きたくなること
さらに以下の症状を伴うこともあります。
・切迫性尿失禁
トイレに間に合わず、尿がもれてしまうこと
日本泌尿器学会によると、日本には800万人の患者がいるとされています。
過活動膀胱の原因には、加齢、脳や神経の病気、前立腺の病気などが関連していることがありますが、原因がはっきりとしないこともあります。
■参考サイト
日本泌尿器科学会
尿路系の異常
尿路系の異常には、主に以下のようなものがあります。
膀胱がん :
膀胱がんになると、腫瘍のできる場所によっては膀胱を刺激するなどして、頻尿の症状が出ることがあります。
ただし、必ずあらわれる症状ではありません。
残尿 :
おしっこをした後でも膀胱に尿が残っている状態です。
おしっこをするときに膀胱がしっかり縮まなかったり、前立腺肥大で尿道や膀胱が圧迫されることで、尿を出し切れないことが原因となります。
尿路系の感染や炎症 :
膀胱や前立腺に炎症が起きると、膀胱を刺激して尿が溜まったと錯覚し、頻回にトイレに行きたくなります。
多くは細菌による感染が原因ですが、ウイルスや薬剤などが原因で炎症を起こす病気もあります。
多尿
尿量が増えることでトイレに行く回数が増えた状態です。1回で出る尿の量が多いのが特徴です。 ( 成人の1回の正常な尿量の目安は200ml~400mlです。 )
多尿の原因としては以下のようなものがあります。
〇 主な原因
・ 水分摂取量が多い
・ 糖尿病
・ 腎臓病
・ 利尿剤などの薬の効果、副作用
心因性
尿路系に異常がないのに、トイレのことが気になって何度もトイレに行ってしまう状態です。
心因性の場合、寝ている間は気にすることができないので、夜間に頻尿の症状がでることはありません。
1日に必要な水分量は?

人の身体は半分以上が水分でできています。
そのため、適切に水分補給が行われないと体調を崩してしまいます。
だからといって、過剰に水分摂取をすると、今度は頻尿の原因になってしまいます。
そこで、1日に必要な水分量は身体の水分バランスが保てる量ということになりますが、具体的に1日の適切な水分量とはどのくらいでしょうか?
成人の場合
成人の場合は、1日に2.5Lの水分が必要とされています。
そのうちの約1.3Lは、食べ物などから摂取されるため、水やお茶などの飲料で摂取する必要があるのは約1.2Lということになります。
〇 1日に必要な水分量 ・・・ 約1.2L
※ 水やお茶などの飲料で摂取する水分
〇 食べ物から摂取する水分の目安
食べ物含まれる水分 ・・・ 約1.0L
食べ物から体内で作り出される水分 ・・・ 約0.3L
---------------------------------------------------
TOTAL ・・・ 約1.3L
〇 1日に失う水分量
尿や便に含まれる水分 ・・・ 約1.6L
息や汗に含まれる水分 ・・・ 約0.9L
---------------------------------------------------
TOTAL ・・・ 約2.5L
■出典
環境省 : 熱中症環境保健マニュアル 2018 「からだの中の水のはたらき」
ビールなどのアルコールは水分摂取にはならない!

ビールやお酒をたくさん飲んでいるから水分摂取はできている!と思う人もいるかもしれませんが、残念ながら、ビールなどのアルコールは水分摂取にはなりません。
逆に、アルコールには、体内の水分を奪う作用があります。
その作用のひとつはアルコールの利尿作用です。
なんと、飲んだアルコール量の倍の水分が尿として排出されてしまいます。
具体的には、ビール1缶350mlを飲むと、350mlの水分補給になるのではなく、身体から750mlの水分が失われてしまうのです。
また、アルコールは分解されるときに水分が必要なため、さらに体内から水分を奪っていきます。
このように、アルコールだけでは水分補給にはならず、逆に脱水が進んでしまうのです。
そのため、アルコールを摂取した場合、1日に必要な水分量を摂取するには、少なくとも摂取したアルコールと同量の水分補給をした上で、さらに1日に必要な水分量を摂取しなければなりません。
頻尿の治療1 - こんなときは医療機関を受診

頻尿だからといって必ずしも医療機関での治療が必要とは限りません。
しかし、頻尿に加え、血尿や下腹部痛、おしっこをするときに痛みがあったり、この後の 「頻尿の治療2 - 薬に頼らない治療」 にあるような生活習慣を見直しても改善されないなど、症状で困ることがあれば医療機関の受診が必要です。
頻尿の治療2 - 薬に頼らない治療
日常生活に支障がでているなどの差し迫った状況でなければ、まずは以下の項目を振り返り、自分でできる改善方法を試してみましょう。
身体を冷やさない
身体が冷えると、血管が縮んで血流が低下するため、膀胱の血流も低下します。
すると、膀胱は正常な働きができなくなり、本当はもっと尿を溜めておくことができるのに、トイレに行きたい信号を発してしまいます。
そのため、冷たい食べ物・飲み物の摂りすぎや、冷房での身体の冷やしすぎなどには注意しましょう。
腹巻をしたり、やけどに注意をしながらお腹にカイロをあてるなどの方法で、膀胱周辺を温めることも効果的です。
水分摂取の仕方や水分量の見直し
尿は、余分な水分を体内から排出する役割を担っているため、当然、必要以上の水分を摂れば尿の量は増えます。
特に、水分を摂りすぎた当日や翌日は多尿となり、頻尿になりやすくなります。
1日2日であればそれほど支障はないでしょうが、連日頻尿で悩んでいる場合は、水分摂取の仕方や水分量を見直す必要があるかもしれません。
まずは1日の水分量をメモするなどして、少しずつ量を減らし、頻尿が改善するか確認してみましょう。
その際、1 日に必要な水分量は下回らないように注意しましょう。
水分摂取を過度に控えると、脱水になったり、他の病気を引き起こしてしまうことがあります。
病院に定期的に通院している場合は、かかりつけの医師に適切な水分量を相談してみましょう。
カフェインを含む飲みものを控える
カフェインには利尿作用があるため、頻尿の原因になることがあります。
カフェインというとコーヒーが有名ですが、エナジードリンクやお茶にもカフェインが含まれています。
頻尿で悩んでいる場合は、カフェインを含む飲み物を控えたり、ノンカフェインの飲みものに切り替えてみましょう。
膀胱訓練 ・ 骨盤底筋訓練
膀胱自体や膀胱、尿道を支えている骨盤底筋を鍛える方法です。
膀胱や骨盤底筋を鍛えることで、膀胱に溜まる尿の量を増やすことができたり、尿を長く留めておけるようになることが期待できます。
そうなると、トイレに行く間隔が伸び、トイレに行く回数を減らすことにつながります。
この訓練は、常におしっこのことが気になったり、トイレがないところは不安で出かけられないなど、おしっこやトイレのことが常に気になるような人に向いています。
反対に以下のような場合には適していません。
〇 膀胱訓練 ・ 骨盤底筋訓練が適していない場合
- おしっこをするときに痛みがある
- おしっこをするときにいきまなければならない
- 泌尿器科的な病気があるとわかっている
- 膀胱・骨盤底筋訓練をすると下腹部に痛みがある
〇膀胱訓練
- 尿道や肛門に力を入れて尿意を我慢する
- 気を紛らわせたり、深呼吸をするなどしてそのまま5分間我慢する
- 我慢できるようになったら、10分、15分と少しずつ時間を伸ばしていく
最終的には2~3時間間隔をあけられるようになるのが目標です。
ただし、我慢しすぎると膀胱炎になる可能性があるため注意しましょう。
〇骨盤底筋訓練
- 仰向けに寝転がり足を肩幅に開く
- 全身をリラックスさせる
- 尿道と肛門(女性の場合は膣も)をゆっくり締める → ゆっくり緩めるを繰り返す
※ お腹に力を入れないようにしましょう
※ 肛門や膣をお腹の中に引き上げるようなイメージで繰り返します
仰向けの姿勢以外にも、座ったり、立った姿勢でもできます。
座る または 立った状態で背筋を伸ばし、同じように尿道、肛門、膣を締める→緩めるを繰り返しましょう。
うまくできているかわからない場合は、清潔な手で肛門や膣の入り口に触れると筋肉の伸び縮みを確認しやすくなります。
頻尿の治療3 - 治療薬 ・ 漢方
頻尿の治療薬には、膀胱の異常な収縮を抑えることで、トイレに行きたくて仕方ないといった尿意切迫感を改善する効果のある薬(抗コリン薬)や、膀胱の筋肉を緩めて膀胱の容量を増やす効果のある薬( β3アドレナリン受容体作動薬)などが使われることがあります。
〇 頻尿の治療にもちいられる漢方
- 八味地黄丸(ハチミジオウガン)
- 牛車腎気丸(ゴシャジンキガン)
- 清心蓮子飲(セシンレンシイン)
- 五淋散(ゴリンサン)
- 猪苓湯(チョレイトウ)
- 小建中湯(ショウケンチュウトウ)
など
どの漢方薬が適しているかは、その人の持っている病気や体質、そのほかの症状、「気血」と呼ばれる東洋医学の考え方により異なります。
詳しくは漢方外来などがある医療機関や漢方専門医の医師に相談しましょう。
頻尿の治療4 - 排尿日誌で尿の状態を把握する
排尿日誌とは、トイレに行った時刻や尿量などを記録することで、尿の状態や症状の特徴、傾向などを把握するためのものです。
また、排尿日誌をつけていると、医療機関を受診した際に、より適切な診断や治療の助けになります。
決まった書式などはありませんが、日本排尿機能学会のWebサイトからダウンロードすることができます。
尿量を計る際は、目盛りのついた計量カップを使うと簡単です。
成人の1回の正常な尿量の目安は200ml~400mlです。
頻尿の治療5 - その他の治療
そのほかの頻尿の治療に 電気・磁気刺激治療 があります。
お腹とお尻にパットをつけ、電気や磁気を通して膀胱や膀胱周囲の筋肉を刺激する治療です。
症状や医療機関によって異なりますが、十数回の治療を1セットとして、週に2回程度の頻度で行っていきます。
1回の治療時間は20分程です。
この治療は、薬物治療をしても効果がなかったり、薬の副作用で治療が続けられない場合には保険が適応されます。
費用は回数や治療の内容によって異なりますが、1セットの治療費は2,500円程度です。※3割負担の場合
高齢者でも受けることができ、副作用もありません。
頻尿と関連した症状
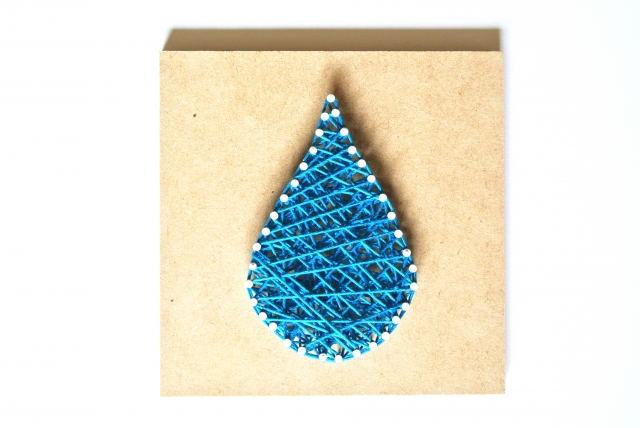
頻尿の原因や治療については前述のとおりですが、そのほかにも頻尿に関連した症状に、以下のようなものがあります。
夜間頻尿
おしっこをするために夜間に1回以上起きなければならない状態です。
特に、加齢とともに腎臓機能の低下などが原因となって、夜間頻尿になることが増えます。
日本泌尿器学会によると、40歳以上では約4,500万人に夜間頻尿の症状があるとされています。
夜間頻尿の原因は以下に分けられます。
- 多尿
- 膀胱容量の減少
- 睡眠障害 ( 眠りが浅い )
■参考サイト
日本泌尿器科学会
夜尿症
夜尿症はおねしょと同じ状態ですが、おねしょは5~6歳ころまでにみられなくなるのが一般的です。
日本泌尿器学会では、夜尿症を以下のように定義しています。
〇 5歳を過ぎて1か月に1回以上の頻度で夜間睡眠中の尿失禁を認めるものが3か月以上つづくもの
引用)日本泌尿器学会
夜尿症は頻尿とは異なりますが、頻尿と同じ病気が原因となっていることがあるため、夜尿症の症状がある場合は、小児科 または 泌尿器科の受診を検討してみましょう。
臓器別 - 隠れている可能性のある病気

頻尿の原因はさまざまですが、関連している臓器によっては病気が隠れている可能性があります。
ここでは、頻尿の症状がある代表的な病気を解説していきます。
腎臓
血液中の不要なものを尿にする臓器です。腰に手を当てた位置の左右に1個ずつあります。
背中寄りに位置しているため、異常があると背中側に痛みが出ることもあります。
腎臓病 :
腎臓は尿をつくる際、尿中の水分量の調整もしています。
腎臓病になるとこの水分調節がうまくできなくなり、水分の多い薄い尿が大量につくられ、多尿の状態から頻尿になることがあります。
尿管
尿をつくる腎臓と尿を溜めておく膀胱をつないでいる管です。
尿管炎 :
膀胱内の尿が尿管に逆流したり(膀胱尿管逆流症)、尿管結石によって尿の流れが滞るなどして、尿管に細菌が入って炎症を起こす感染症です。
炎症による刺激で頻尿の症状があらわれます。
膀胱
尿を一時的に溜めておく袋状の臓器です。
尿が溜まって膀胱が引き延ばされると、尿意を感じて排出するようにできています。
膀胱炎 :
一般的な膀胱炎は、尿道から細菌が入り、膀胱で感染して炎症を起こす感染症です。
炎症による刺激で頻尿の症状があらわれます。
頻尿のほかにも、おしっこをするときの痛みや残尿感などの症状をともなうことがあります。
間質性膀胱炎 :
一般の膀胱炎とは異なり、尿の成分が膀胱の壁に染み込むことで起こると考えられている慢性の膀胱炎です。
炎症による刺激で頻尿の症状があらわれます。
膀胱がん :
腫瘍のできる場所によっては、膀胱が伸びなくなったり内側が狭くなることで尿が溜めにくくなる、膀胱が刺激されるなどして頻尿となることがあります。
頻尿のほかにも、血尿やおしっこをするときの痛みなどの症状をともなうことがあります。
尿道
尿を膀胱から体の外に出すための管です。
尿道炎(性感染症) :
性感染症のひとつです。
性行為によって、細菌や真菌、ウイルスが尿道に感染し、炎症を起こします。
尿道炎を起こしやすいのは尿道が長い男性で、主な原因は淋菌とクラミジアです。
少しでも尿がたまると、おしっこをして尿道から細菌などを洗い流そうとするため頻尿になります。
女性の場合は尿道が男性の1/4と短いため、細菌などが入り込んでも尿道での感染は起こりにくく、膀胱で感染を起こし、膀胱炎になることが多いです。
前立腺
前立腺は男性だけにあるクルミほどの大きさの臓器です。精液の一部である前立腺液をつくります。
膀胱のすぐ下で尿道を取り囲むように位置するため、前立腺の病気が頻尿の症状を引き起こすことがあります。
前立腺肥大症 :
前立腺が大きくなる病気です。
前立腺が大きくなると、前立腺の中心を通る尿道を圧迫して、尿の出方が弱くなり、膀胱に溜まった全ての尿を出し切れなくなる場合があります。
すると、すぐにまた尿が溜まってしまうため、頻尿になります。
そのほかにも、前立腺が大きくなり膀胱を押し上げると、膀胱に溜められる尿の量が少なくなって、頻尿につながることがあります。
前立腺炎 :
急性と慢性があります。
急性前立腺炎の場合は、前立腺が細菌に感染して炎症を起こします。
一方、慢性前立腺炎の場合は必ずしも細菌が原因とは限りませんが、何らかの理由で前立腺が炎症を起こします。
どちらも炎症による刺激で頻尿の症状があらわれます。
頻尿のほかにも、おしっこをするときに痛みを感じる、おしっこがでにくいなどの症状があらわれます。
急性前立腺炎は慢性前立腺炎に比べると症状が強くあらわれやすく、さらに発熱することがあります。
慢性前立腺炎で発熱の症状がみられることはありません。
子宮
女性だけにある臓器です。
尿路系の臓器ではありませんが、膀胱の後ろに位置するため、子宮の状態が頻尿の症状を引き起こすことがあります。
子宮筋腫 :
子宮の壁にできる良性の腫瘍です。
筋腫の位置や大きさによっては膀胱を圧迫して、頻尿の原因になります。
子宮内膜症 :
子宮内膜は、子宮の内側を覆う粘膜の部分です。
この子宮内膜が剥がれおち、経血となって排出されるのが生理ですが、子宮内膜症は、本来、子宮の内側にある子宮内膜が、子宮以外の場所にもできてしまう状態です。
子宮以外でできる場所はさまざまですが、膀胱やその周辺にできることがあります。
そうなると、その部分が膀胱を圧迫したり、炎症を起こして膀胱を刺激し、頻尿の症状につながります。
また、膀胱の中にできると、血尿の症状があらわれることがあります。

