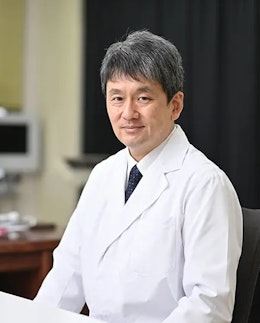緑内障とは、症状や診断、治療方法について

医師紹介
2001年獨協医科大学医学部卒業、順天堂大学附属順天堂医院眼科、市立室蘭総合病院、順天堂静岡病院、賛育会病院眼科部長を経て、2018年より井上眼科医院の3代目院長に就任。日本眼科学会認定眼科専門医、日本緑内障学会所属、栃木県眼科医会理事。
目次
緑内障とは
緑内障は、目から入ってきた情報を脳に伝達する視神経が眼圧によって障害されることが原因で、見える範囲が狭くなったり視力が低下したりする眼疾患です。はじめは自覚症状がほとんどないため、緑内障が進行して治療が遅れると失明に至る場合もあります。症状がなくても定期的に検診を受け、早期に緑内障を発見して眼圧を下げる治療を続けることが大切です。
緑内障の発症と大きく関係する「眼圧」とは
眼圧とは、目の中を満たしている液体(房水)による眼球内の圧力のことで、眼球は房水が常に循環することで眼圧を一定に保ち、水風船のように丸い球状を維持しています。しかし、何らかの原因によって房水の排出口である隅角の流れが悪くなったり、塞がったりしてしまうと眼球内に房水が溜まり、眼圧が上昇します。眼圧が高いとその圧力で視神経が圧迫されて減少し緑内障を引き起こしてしまうため、房水を循環させて眼圧を適正に保つことが重要になります。
緑内障の種類
・開放隅角緑内障(かいほうぐうかくりょくないしょう)
開放隅角緑内障は、眼球内の房水の流れが悪いため眼圧が上昇する慢性緑内障の1つです。慢性的に視神経が圧迫され、視野障害なども徐々に進行します。眼圧が正常レベル(20mmHg以下)の「正常眼圧緑内障」も開放隅角緑内障に含まれます。
・閉塞隅角緑内障(へいそくぐうかくりょくないしょう)
閉塞隅角緑内障は、房水の出口である隅角が狭くなり眼圧が上昇します。慢性型と急性型があり、眼圧が急激に上がり目の痛みや頭痛、吐き気などの「急性緑内障発作」を引き起こすと、症状によっては数日で失明にまで至ってしまうケースもあるため緊急の対応が必要です。
緑内障の症状
緑内障を発症してしまうと少しずつ視野が狭くなっていきますが、軽度の眼圧上昇とともに自覚症状がないままゆっくり進行するため、気づかないことがほとんどです。一般に多い開放隅角緑内障では、中期~末期になって視野欠損があらわれます。閉塞隅角緑内障では、急性発作を起こす前の眼圧は正常なことが多いので自覚症状はありません。しかし、発作後には眼圧が急激に上昇するため、見え方に異常がでるほか、強い頭痛や目の痛みを伴います。
緑内障は誰にでも起こる病気ですが、特に下記に当てはまる場合は緑内障になりやすい人といえるかもしれません。
- 40歳以上の方
- 睡眠時無呼吸症候群の方
- 高血圧、低血圧の方
- 糖尿病の方
- 緑内障の近親者がいる方
緑内障の診断
緑内障の診断では、主に以下の3つの検査を行います。
| 眼球内の圧力を測る検査。眼圧の正常値は10~21mmHgだが慢性緑内障では眼圧が正常値の場合も多い。 | |
| 眼底(目の奥)の血管や視神経、網膜の状態を調べる検査。視神経に障害があると視神経乳頭陥凹(ししんけいにゅうとうかんおう)が大きくなったり変型したりする。 | |
| 視野の範囲を測定し、視野の欠け具合や障害の程度から緑内障の進行具合を調べる。 |
これらの検査によって視神経が減った場所があり、視野の異常が見られた場合に緑内障と診断されます。そのほか、検査用のレンズを入れて隅角を観察する隅角検査や、結膜や角膜などの前眼部を観察する細隙灯(さいげきとう)顕微鏡検査なども行い、緑内障の種類を決定します。
緑内障の治療

緑内障は自然に治る病気ではないため、眼圧を下げて視神経の障害を抑えたり、進行を遅らせたりして改善することが基本的な治療アプローチです。目の状態や緑内障の進行具合によって、点眼薬やレーザー治療、手術などを行います。また、眼圧が上昇する原因になる喫煙やうつぶせ寝などはできるだけ控えるようにします。
開放隅角緑内障の治療
開放隅角緑内障と診断された場合は、眼圧を下げることで視神経が減らないようにして、視野障害の進行を抑えます。眼圧の正常値は10~21mmHgといわれていますが、個人差があるため患者さんの平常時の眼圧(ベースライン眼圧)からどの程度下げられるかが重要になります。
●点眼薬による治療
一般的には、まず眼圧を下げるために点眼薬を投与します。点眼薬には、房水の排出を促すことで眼圧を下げる「プロスタグランジン関連薬」や、房水が作られるのを抑制して眼内の房水量を減らす「炭酸脱水酵素阻害薬」など、さまざまな種類があります。通常はプロスタグランジン関連薬などの点眼から始めて、効果や副作用など患者さんの状態を見ながら調整し、治療を進めていきます。
●手術による治療
点眼薬を続けても眼圧が下がらず病状が進行する場合は手術を行います。房水が排出される部分(線維柱帯)にレーザーを照射して排出を促すレーザー療法や、手術で線維柱帯の一部を取り除く「線維柱帯切除術」、線維柱帯を切り開いて排出部を回復させる「線維柱帯切開術」などがあります。手術は点眼治療よりも眼圧を下げる効果が大きいですが、合併症のリスクもあるので医師とよく相談することが大切です。
閉塞隅角緑内障の治療
閉塞隅角緑内障では、急激に眼圧が上がる急性発作を防ぐことが重要です。点眼や内服、点滴などの薬物療法で眼圧を下げるほか、房水の排出口を塞いでいる虹彩にレーザーで小さな孔を開けて隅角が閉塞を防ぐ「レーザー虹彩切開術」があります。また、白内障手術を応用として、水晶体を取り除き厚みが薄い人工の眼内レンズに変更する手術も選択肢の一つです。この手術を行うことによって隅角が開きやすくなり、急性発作が起きにくくなります。薬物治療やレーザー虹彩切開術を行っても眼圧が下がらない場合にはこの手術が必要です。
まとめ
今回のコラムでは、中高年に多い緑内障についてご紹介しました。失明の原因疾患1位となっている緑内障ですが、できるだけ早く発見し、治療を続ければ決して怖い病気ではありません。目の不調は日常生活にも大きな支障がでるので、年齢にかかわらず定期的に目の検診を受け、気になる症状があれば早めに眼科を受診しましょう。
出典・参考文献
・公益社団法人 日本眼科医会「よくわかる緑内障―診断と治療―」
・公益社団法人 日本眼科医会「緑内障といわれた方へ―日常生活と心構え―」
・参天製薬株式会社「目の病気百科-緑内障-」